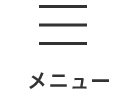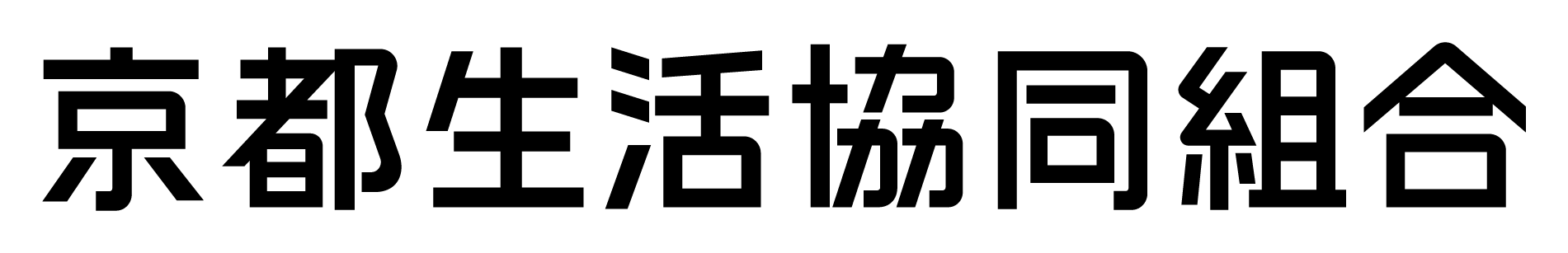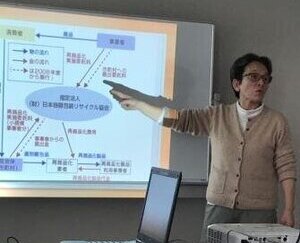みんなのとりくみレポート
「プラごみ問題」学習会
- 南ブロック
- 2020年02月11日
- 主催:京田辺Bエリア会
- 開催日:2020年2月 3日 / 月曜日10:00~11:30
- 開催場所:京田辺市社会福祉センター第2研修室
NPO法人、コンシューマーズ京都の有地淑羽さんを講師に迎え、「プラごみ問題学習会」を開催しました。
家庭から出る「使い捨て容器・包装プラスチック調べ」のアンケート結果をもとに、プラごみの現状について説明していただきました。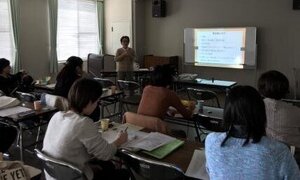 アンケートを提出した方からは、「生ごみより圧倒的にプラごみが多いのですが、衛生面、安全面、便利な面でプラの恩恵を受けている」「容器包装を減らす難しさも感じた」「食事を簡単に済ませようとするとプラごみが増える」などの感想が寄せられ、その後工夫したこととして、「エコバッグを持ち歩いた」「マイボトルを持参した」「紙容器の飲料を買った」などの意見が出されていました。
アンケートを提出した方からは、「生ごみより圧倒的にプラごみが多いのですが、衛生面、安全面、便利な面でプラの恩恵を受けている」「容器包装を減らす難しさも感じた」「食事を簡単に済ませようとするとプラごみが増える」などの感想が寄せられ、その後工夫したこととして、「エコバッグを持ち歩いた」「マイボトルを持参した」「紙容器の飲料を買った」などの意見が出されていました。
こうしたプラごみ問題の現状を、どのようにしていけばよいのかをエリア会でも交流しました。
私たちの事前質問として、「プラマークってどういう意味?」という素朴な疑問にも、「容器包装リサイクル法」と合わせて答えていただきました。
今のプラごみのリサイクル法でも完全に環境に良い処理ができているとは言えないので、私たちにできることはやはりプラごみの排出量を減らすことが一番で、まず関心を持つことが大切だということがわかりました。

私たち消費者には社会を変えていく力があり、たとえば食品を選ぶ際であれば味、価格、利便性などに加え「容器」の選択肢を1つ増やすこと、容器包装のことを考える仲間を増やす意味で家族の協力を得ること、消費者の意見をお客様の声としてメーカーや生産者へ届ける声を出すことなど、これから私たちにできることはたくさんあることがわかりました。
≪エリア会の感想から≫
ごみについて疑問を持っている人は多いと思うので1人1人が周知できる体制を市などが作ってほしいと思った。
京田辺市のごみガイド冊子をもっと詳しくわかりやすいものにしてほしいと思った。
大まかに分別していたけど、もっときちんと分けていこうと思った。
知ろうという好奇心をいつも持てる自分でいたい。
最後のエリア会でプラごみ問題学習会ができてよかった。
何となく過ごしている毎日が意識をすることで変わった。
![]() バックナンバー
バックナンバー
お問い合わせ・申し込みは、各ブロックまで
- 北ブロック
- 電話番号 0120-075-028
左京区・北区・上京区・中京区・下京区
- 東ブロック
- 電話番号 0120-075-129
東山区・山科区・伏見区・南区
- 西ブロック
- 電話番号 0120-075-136
右京区・西京区・向日市・長岡京市・大山崎町・亀岡市・南丹市・京丹波町
- 南ブロック
- 電話番号 0120-075-238
宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町・木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村
- 両丹ブロック
- 電話番号 0120-075-262
綾部市・福知山市・舞鶴市・宮津市・与謝野町・伊根町・京丹後市